文部科学省が学習指導要領の中で、「生きる力」を学校で育むことを盛り込みました。また、幼児教育の中でも生きる力の基礎3つの柱というのは、保育指針の軸とされています。
ただ、「生きる力」といっても幅広い解釈ができるため、いまいちピンとこないママも多いです。今回は、教育や保育で重要視される生きる力とは何を指すのか、保育指針の中心となる生きる力の基礎3つの柱を解説します。
家庭だけではわからない日本の教育の本質について、今一度考えてみましょう。
幼稚園と保育園の指針「生きる力の基礎3つの柱」とは

幼稚園や保育園で子どもを保育する場合、幼児教育をどの先生も学びます。子どもを育てるにあたって大切な要素とは、生きる力の基礎3つの柱が基本となるのは、幼児教育に触れたことのある人にとっては当たり前かもしれません。
ただし、子育てとして子どもと触れ合うママにとっては3つの柱、3本柱はなじみの薄いものですよね。そこで、まずは生きる力の基礎3つの柱とは何かをわかりやすく説明します。
幼児教育を行う施設として共有すべき事項の育みたい資質・能力
生きる力の基礎3つの柱とは、保育施設を運営する・保育施設で保育を行うにあたって、必ず履修する「保育所保育指針」や「幼児教育要領」などに記されている「幼児教育を行う施設として共有すべき事項の育みたい資質・能力」に記されています。
教育関係者だとこの全文を知り、記憶していることも珍しくありませんが、それほどまでに教育関係者が持っておきたい「前提の心構え」がこの指針には盛り込まれています。
生きる力の3つの基礎は、この文言に書かれている文章のことです。
・豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする「知識及び技能の基礎」
・気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力,判断力,表現力等の基礎」
・心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力,人間性等」
保育所保育指針
保育の目的はこの3つに集約され、これを総合的に表したものが「生きる力」です。
幼児教育だけでなく、文部科学省の学習指導要領でも生きる力が盛り込まれるなど、今子どもの教育・保育において欠かせない要素といえるでしょう。
3つの柱は10の姿と5領域の基本
この3つの柱というのは、保育が目指す10の姿と5領域の基本になっています。少し難しい考え方ですが、今の保育の指針を知るために簡単にチェックしてみましょう。
10の姿…5領域を育んだあとに目指す姿のこと
- 健康な心と身体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 数量・図形、文字などへの関心・感覚
- 言葉による伝えあい
- 豊かな感性と表現
このように、保育園や幼稚園で行われる保育、学校で行われる教育には、基本的な考え方がありそれぞれにねらいや目標が設定されています。
生きる力の基礎3つの柱を解説

では、生きる力の基礎3つの柱はそれぞれどういう意味を持つのかご紹介します。
今教育の場面で問われている「生きる力」を理解するためにも一つずつ見ていきましょう。
知識及び技能の基礎
知識及び技能の基礎とは、難しい書き方ですが端的にいうと「体験し何かを得る」という意味を持ちます。
知識、技能というと座学で得る学習能力や運動が単純によくできるというイメージを持たれがちですが、決してこれだけが知識と技能ではありません。例えば、散歩に出かけて季節の移ろいを感じる、枯葉や木の実などを使って作品で表現するという屋外活動でも、さまざまな体験と知識が得られます。
難しく考えなくても、子どもにとっては些細なことが大きな経験のひとつです。この知識及び技能の基礎を重ねて、子どもの情緒と成長を育みます。保育施設では体験を特に重視しますが、家庭でも子どもにたくさんの経験を与えられるでしょう。
思考力、判断力、表現力などの基礎
次は、1つめの「知識及び技能の基礎」で培ったものを、さらに発展させる「思考力、判断力、表現力などの基礎」です。
先ほどの活動と続けて考えると、散歩に出かける前に「そろそろ葉っぱの色が変わり、落ち葉を拾うことができる」と想像し、「この葉っぱを使って遊びたい!」と思いつき、落ち葉のじゅうたんやおままごとに利用して子どもが思い思いに遊んだ、という体験が該当します。
子どもの発想力は大人の想像以上に高いです。この自由な発想を表現できる環境を作ってあげることが、この能力を培うために大切です。
学びに向かう力、人間性など
子どもの心が成長し、向上心を持ち生活するようにする力を指します。3つめの柱である「学びに向かう力、人間性など」では、1つめ、2つめと比べると全体を包括するような力が求められています。
この力は言われた通りに勉強できる力でも、大人の言う通りに黙って座っていられる力でもありません。この柱で大切なのは、「心・意欲・態度」が育つ中で、より育んでいきたいことという点です。
生きる力とは、さまざまな要素で構成されていますが、単純な「良い子」というのは大人の言う通りに動く子ではないことがわかりますよね。自分の意思を持ち、興味を持つものへの探求心があり、人間として強く生きる方法を教えることこそ、今の教育に求められています。
今見直される「生きる力」の基礎

生きる力の基礎というのは、これまでのママ達が受けてきた教育とは少し異なる観点から評価されるものです。「今と昔は違う」という点を正しく理解するために、今見直される生きる力についてもう少し踏み込んで考えてみましょう。
これからの教育はゆとりでも詰め込みでもなく「生きる力」
これまでの教育は「ゆとりをもってのびのびと」というものでも「とにかく詰め込む」というものでもありません。これまでと違う考え方なので、生きる力というのは大人にとってはなじみが少なく「なんだかよくわからない…」と思うかもしれません。
ただ勉強ができる・頭がいいというだけでなく、現代の移り変わる社会構造に柔軟に対応できる人間力のある人が求められます。今、生きる力が見直されているのも、グローバル化や情報化が進む社会情勢を考慮した結果です。
家庭でもできるところから基礎を育む
なんだか難しく思える「生きる力」ですが、生きる力の基礎3つの柱を考えてみても、実は簡単なところから生きる力が育めることがわかります。
家庭でも小さな体験を重ねてみたり、幼稚園や保育園、学校で学んだことを日常生活でも応用してみましょう。家庭での親子体験を、学校で話すことも立派な「生きる力」を育てる学習です。
子どもが興味を持つものをママが見つけて、その興味を広げる工夫をしてみてもよいかもしれません。何も特別なカリキュラムは必要ないので、少しだけ子どもの興味に目を向けて親子で一緒に生きる力を育ててみましょう。
昔と今の教育の違いに注意!
生きる力が注目される背景に、社会構造の変化があります。この「生きる力の基礎3つの柱」を見てみても、「自分たちの幼少期とは雰囲気が違うなあ」と感じるママも多いでしょう。
自分のころはこうだったから、といって同じように子どもに求めても、うまくいかないことも多いです。もちろんママの経験を生かした育児は大切ですが、現代の子どもがどのような能力を育むとよいのかは、情報を常に新しくしてママ自身も柔軟に考えてみましょう。
生きる力とは単純なもので、決して難しいことはありません。少し気分を楽にして、肩の力を抜いて子どもを一人の人間として見つめなおすと、教育の原則が理解できるかもしれませんね。
まとめ
今注目されている「生きる力の基礎3つの柱」。保育指針という教育や保育に触れていない方から見ると少し難しい考え方ですが、その仕組みは決して複雑なものではありません。
社会構造の変化は激しく、保育に求められるものも子どもにとってよい環境も、常に見直されています。新しい情報を取り入れて、柔軟に子どもと接するようにしてみましょう。
【参考】
3本柱ってどんなもの?育みたい資質・能力の3つの柱について考えてみよう! | ココキャリegg
保育の5領域とは?3つの柱・10の姿との関係や実践例を紹介! | 保育園・幼稚園向けのICTシステム|Child Care System
文部科学省が定めた「生きる力」って?学校教育はどう変わるの? | ママソレ| 子育てママのくらしがちょっぴり軽くなる生の声メディア




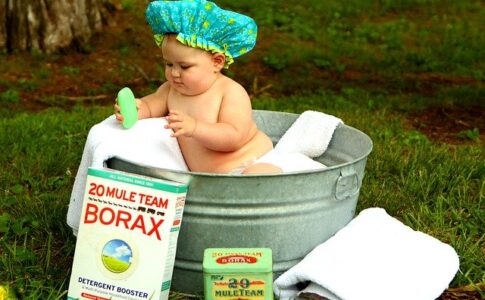
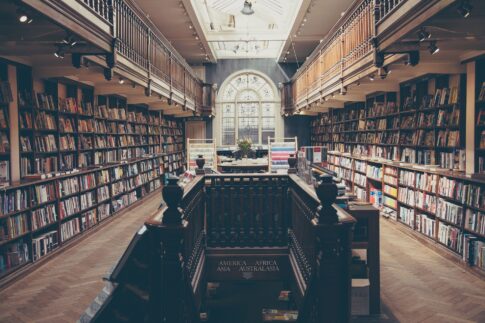










5領域…保育のねらいを5種類に分けたもの