最近よく目にするようになったHSP(ハイパーセンシティブパーソン)。HSPは人一倍外部からの刺激に敏感で、繊細な人を指します。
HSPは病気ではないとはいえ、ママがHSPの場合子育てのイライラや子どもに関する人付き合いでかなり苦労することも。また、子どもにもHSPは存在し、これはHSC(ハイパーセンシティブチャイルド)と呼ばれます。
今回はHSPの子育てと、我が子のHSCとどう向き合うかを、公認心理師監修のもと解説。HSPについて正しい知識を身につけ、親子が笑顔で過ごせる環境を目指しましょう。
病気でも一時的なものでもない、「HSP」とは?

HSP、HSCとは病気でも一時的なものでもありません。一般的に人よりもはるかに感受性が高く、外部からの刺激でストレスが溜まりやすい繊細な気質を持つ人のことを指します。
まずは、HSPやHSCとは何か詳しく見ていきましょう。
HSPとは「人一倍感受性が高く繊細な気質を持つ人」のこと
最近よく目にするようになったHSP。これはハイパーセンシティブパーソンの略称であり、「人一倍敏感で感受性が高く繊細な気質を持つ人」を指します。
HSPを語る上で、HSPを提唱したアメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン氏は以下の特徴があると呼びかけています。
よく物音に強い刺激を受けすぎる聴覚過敏や、口にするものが限られる味覚過敏と同じ意味合いで使われますが、HSPは神経症などとは異なります。病気や障がいではなく、持って生まれた性格や気質です。
また、育ってきた環境や外部の刺激でHSPが起こることもありません。ママの中には「普通の人には耐えられることが、自分にとってはとても苦痛に感じる」「一般的な感覚では説明のつかない部分が自分の中にはたくさんある」「心を病みやすく、他人から言われたことに強く反応してしまう」といった心当たりがある方もいるかもしれませんが、それはHSPなのかもしれません。
深い洞察力と感受性の高さは、決してネガティブなことばかりではありません。芸術や音楽など、感性を生かして活躍するHSPもたくさんいます。ただし、普通に生活するだけでもストレスが溜まりやすい世の中で、HSPはより多くの物事を受け止めすぎて考え込んでしまう傾向にあることは事実です。
その生きづらさは気質のせいかも?HSPの特徴
実際にDOESという特徴を持つHSPですが、次にHSPの特徴をチェックリストでご紹介します。比較的新しい概念であるため、これまでHSPであったにもかかわらず気づかずに生活していたママも多いかもしれません。
- 大きな音や強い匂い、光などをひどく不快に思うことがある
- 将来や少し先のことに対して失敗を予測してしまい、毎日かなりの心配で疲れている
- テレビや映画で暴力的なシーンを見ると、その後何日も影響してしまう
- ちょっとしたことですぐに涙が出てしまう
- 他人と数時間一緒にいただけで疲れ果ててしまい、翌日にも影響が出る
- 誰かの怒りを見たり感じたりすると、自分に向けられたものでなくてもストレスに思う
- 社交の場が苦手、多数の人と一緒にいることが苦痛に感じる
- アポイントなしの訪問を苦手に感じる
- ニュースなどで辛い情勢を知ると、違う国のことでも心を痛めることが多い
以上の項目の中で、当てはまることが多ければHSPの傾向があります。
HSPは決して珍しいことではなく、また悪い病気でもありません。ただ、自分が楽しく生きやすくするためには、人とは違うちょっとした工夫が必要です。
子どものHSPは「HSC」と呼ばれる
次にHSC(ハイパーセンシティブチャイルド)についてご紹介します。HSCとはこれまでお伝えしたHSPが幼児期から見られることを指します。子どものHSPだととらえておきましょう。
HSPは向き合い方次第で感性をコントロールできますが、HSCはまだ子どもであるためなかなかうまくいきません。例えば、以下のような特徴があればHSCが疑われます。
- すぐにびっくりする
- 洋服のタグや生地のチクチク感、靴下の縫い目を気にしやすい
- しつけをするとき、強く語気を荒げるよりも優しく語りかけたほうが効果がある
- 親や先生など大人の心を読む
- 匂いに敏感で普段の匂いと違うことに気づきやすい
- ユーモアのセンスがあり、感受性も独特
- 大きな変化に対応できない
- 静かに少人数で遊ぶことを好む
- 物音に敏感でなかなか寝付けない、決まった場所でしか眠れない
- 発表会や運動会など、たくさんの目がある場に出るのが苦手
このほかにもHSCの特徴は人それぞれですが、総じてHSPと同じように「外部からの刺激を強く受け止めすぎる」傾向にあります。
理由もなくぐずることが多かったり、子どもが喜ぶであろう遊園地やテーマパークなどを嫌がったり、幼稚園や小学校の集団生活になじめなかったりといった我が子の特徴があれば、その気持ちを汲み取る必要があります。「なんだか周りの子とは違うのかも…」と思ったら、HSCを正しく理解してあげることが重要です。
HSCは確かに繊細さんな分ママとしては育児ストレスが募りますが、どんなに言葉を尽くしても叱っても治るものではありません。大人が子どもの環境を変えない限りは、生活するので精一杯であることに気づいてあげましょう。
HSPで子育て中のイライラが止まらない…。HSPの子育てポイント

次は、ママがHSPの場合の子育てを考えてみましょう。感受性の高いHSPですが、これは持って生まれた気質なので我が子が理解してくれるかというとそうではありません。その分理解者が少なくママも育児での孤立感を高めやすいため、注意が必要です。
HSPが子育てをするにあたって、いくつかのポイントをご紹介します。
子育てはそもそも「大変なもの」と認識して
HSPは感受性が高い分、育児に対しても問題や辛さを抱え込みがちです。
- 周りのママだって同じように辛いんだから、こんなの大変なうちに入らない
- 私がここまで辛いんだから、パパにお願いするのは申し訳ない
- 子どもの声が大きい気がするし、ベビーシッターにも迷惑がかかるかも…
このように必要以上に回りに遠慮してしまい、周囲に正しくSOSを出せません。
子育てはどんな状況であれ、周りに協力してくれる手がたくさんあったとしても大変です。その家庭それぞれで大変さは異なり、比較できるものではありません。
子育てはそもそも大変なものと認識して「みんな頑張っているんだから」ではなく「私はとっても辛い、私にとってはとても大変だ!」と思ってもよいのです。自分を許してあげられるのは自分だけということを、今一度認識すると気持ちが楽になるかもしれません。
気になる物音やノイズは徹底的に減らす
HSPは物音やノイズ、光などに反応しやすいことが多いです。子どもと寝かしつけて一緒に寝るママも多いですが、繊細な分我が子であっても何度も目が覚めて物音や光でゆっくり休めないかもしれません。
この物音やノイズの刺激は、徹底的に減らすのがおすすめです。
- 子どもが常夜灯でしか眠れない場合、就寝場所を分ける
- 加湿器やエアコンの光りが気になる場合、目張りをする
- アイマスクや耳栓を使用する
- 気持ちに余裕がなくなったら静かな場所に避難する
「普通はこんなことはしないのかも?」と思っても、自分の中の常識で判断しましょう。子どもが小さなうちは耳栓やアイマスクが使えず目が離せないかもしれませんが、危険がなく周囲に迷惑が掛からない状態であれば「子どもが泣いているけれど少し自分の気持ちを落ち着けるために離れる」のもOKです。
特に実家への帰省や旅行中はHSPだと眠りにつけないこともあります。自分を守るために、周囲の刺激を和らげるグッズは携帯しておくとよいでしょう。
周囲の協力を上手に得る
子育てはただでさえ手が足りないのに、繊細でため込みがちなHSPだと限界がすぐに訪れます。努力だけでは解決できない問題も多いため、周りの協力を上手に得ましょう。
とはいえ、お願いするのが得意な人が多いかというとHSPに限ってはそうでありません。おすすめは自分が何かをするときに一緒にお願いすることです。
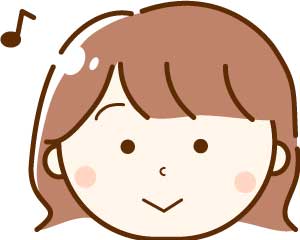
「今から食器を洗うから、子どもたちのお風呂お願いできる?出たら寝支度は私がやるね」

「この部屋を片付けておくから、寝かしつけお願いしてもいい?」
など、自分にもやるべきことがある状態で一緒にお願いすると、気持ちも楽になりハードルも下がります。
周りと比べない。早めに休みを取る
「でも子育ては誰でも大変なんだから…」と自分の意見を一般的なものに寄せてしまうのも、HSPの特徴です。必ず周りと比べず、自分にとっての辛い、限界を見極めて早めに休むようにしましょう。
誰かと比べてしまうと、どうしても周囲のほうが恵まれていて優れているように感じます。また、その感性を受けやすいのがHSPです。SNSやネット上には情報がたくさんあふれていますが、ときには「あえて見ない、知らないでおく」というのも大切です。
自分の気持ちを最優先にするのはすぐにできることではありませんが、子どもにもイライラせずに接するためにもママは必要最低限の工夫をしておきましょう。
HSCの子どもとの向き合い方

次はHSC(ハイパーセンシティブチャイルド)について解説します。これはHSPの気質を持つ子どものこと。我が子が人一倍繊細だった場合の育児の仕方です。
繰り返しお伝えしているように、HSPもHSCも病気や障がいでは決してありません。どんなに育児を頑張っても、生まれ持った気質を変えることはできません。
ただママができるのは、HSCを正しく理解して家庭と親を子どもの「安全基地」にしてあげることです。HSCについて、詳しく見ていきましょう。
「泣き止まない」「寝ない」HSCとは
HSCとは記事冒頭でもお伝えした通り、ハイパーセンシティブチャイルドの略称です。大人にみられるHSPと同じ状態の子どもであり、こちらも最近よく目にするようになりました。
特徴はお伝えしたような繊細さ、感受性の強さがありますが、こだわりが強く個性のある発達障がいの伴う症候群ではありません。自閉症スペクトラム症候群の場合は「他人の気持ちを推し量るのが苦手」であるのに対し、HSCは「他人の思いを汲み取りすぎてストレスを溜める」という特徴に違いがあります。
どんな検査をしても知能や特性に問題は見つからないのに、「なんとなく育てづらい」「他の子とは違う、とてもユニークに感じる」という場合はHSCかもしれません。また、HSCは生まれ持った気質だからこそ人によって状況はさまざまで「これ」といった解決法は存在しません。
多くのママが我が子がHSCだと勘づいたときに、「子どもなら喜ぶはずと思ったサプライズが通用しなかった」という声があります。例えば遊園地に連れていったのに楽しめなかった、バースデーパーティを開いたのに不満そう、といったHSCの特徴が当てはまるでしょう。
HSCは遺伝する?
HSC並びにHSPは遺伝するかというと、これは明確に研究結果が出ていません。一般的には、感受性が非常に高い親の子どもがHSCかというと半数程度の割合であり、必ずしも遺伝するわけではないのが結論です。
ただ、ママがHSPやHSCに理解があれば、我が子への向き合い方や声掛けの方法も変わるかもしれません。反対に理解が薄いと、子どもは疎外感を覚え家庭に対して安心感を抱けなくなってしまいます。
HSCの子育ての特徴
HSCを育てるにあたり、いくつか悩むことがあります。
- 子どもの「当たり前」が通用しない
- すぐに泣いてしまう、あやしてもなかなか泣き止まない
- 良かれと思ってやったことを全力で拒否される
- 繊細でいろんなところに気がかりがある
- 寝つきが悪い、お出かけに行くにも気を遣う
繊細でさまざまなところに気を遣ってしまう分、子どもは疲れやすくママも対応に困りがちです。ときには気質が理解できず、「なんでうちの子は周りの子と違うの?」とイライラしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、このHSCは治そうと声掛けをしたりしつけをしても、まったくの無意味です。むしろ大人の気持ちを考える特性上、余計に子どもが委縮してしまうかもしれません。
まずはママもパパもHSCをしっかり理解し、子どもがどのような生きづらさを抱えているかを考えながら向き合っていきたいですね。
HSCについて詳しくはこちらの記事もチェック▼
HSCにとって「小学校」とは?

小さなうちは家庭や保育園、幼稚園といった大人に囲まれた環境で過ごすため、HSCでも特に問題が起こらないかもしれません。もし集団生活を苦手としていても、少人数制の園を選んだりと対策ができるからです。
しかし、小学校に上がると状況は変わってきます。小学校ではさまざまな配慮も行き届かないことがあるため、HSCはストレスを多く抱え通えなくなったり小学校に苦手意識を持ったりもするでしょう。
ここからはHSCにとっての小学校生活を考えます。我が子が小学校になじめずどうしてよいのか悩んでいるママは、ぜひ参考にしてください。
HSCにとって小学校は「ストレスフルな場所」
HSCにとって小学校とは、ストレスでいっぱいの場所です。ママの中には「たくさんのお友達がいて楽しく遊べる、給食も食べられる素晴らしいところ」と思うかもしれませんが、HSCにとってはたくさんの同級生に囲まれて家庭とまったく異なる状況で、決められた時間の中で物事に取り組まなければならないとどれもストレスの強いものばかりです。
つまり、何歳になってもHSCは「小学校に通っているだけでとても頑張っている」と認識しておきましょう。過度に子どもに期待したり強要したりするのではなく、子どもなりに折り合いをつけて小学校に行っているだけで満点です。
また、クラス替えの時期や席替えのタイミング、運動会など行事の準備が始まると余計にHSCは悩むことが多くなります。子どもの情緒が不安定になりがちなため、我が子の苦手とする期間をあらかじめ把握しておくと、親としても心構えがしやすいでしょう。
小学校に上がる前にママが知っておきたいこと
うちの子はHSCと認識がある場合、小学校に上がる前にやっておきたいことがあります。
- HSCとして気を付けたいこと(光が苦手、大きな物音が苦手など)があれば担任と共有する
- 小学校に無理に通わせようとしない
- 子どもに小学校は楽しいものと誇張して伝えない
- 同じHSCの親と情報共有する
可能であれば、以上のことに留意して子どもの小学校生活を応援したいですね。
ただ、小学校生活ではさまざまな体験があるため、万全な対策はできません。もし子どもが小学校に疲れたり限界が訪れそうであれば、ママは一番の味方になってあげてお話をしてあげましょう。
小学校でトラブルが起きたら?
どう対策をしていても、人一倍繊細な分小学校に通えなくなることもあります。また、人の思いを汲み取りすぎてお友達とトラブルになったり、授業にうまく集中できないこともあるでしょう。HSCに理解のない教師に困ることもあるかもしれません。
小学校でのトラブルが起きても、HSCに無理に事情を聞くのはおすすめしません。まずは子どもが話したくなるまで、ただ待ってあげましょう。
また、年齢を重ねるごとにいろいろなことが起こります。前年で起きたことや家庭での様子をできる限り担任の先生と共有し、協力を求められるとベストです。先生からも学校での様子を聞いてみると、できることが見つかるかもしれません。
HSCと小学校の関係は以下の記事でまとめています▼
HSCで不登校に…。親はどう対応する?

HSCの親としてとても心配なのが、「子どもが学校に通わなくなったとき」です。不登校になったらどうすればよいのか、ここからはHSCの不登校について考えていきましょう。
子どもの気質を正しく理解し味方になる
まず、HSCとは何かを今一度考えなおしましょう。人一倍繊細で、外部からの刺激に強く反応してしまい、人の気持ちを汲み取りすぎるために行動ができなくなる気質がHSCです。また、これは病気でも障がいでもなく、HSC本人にもどうしてよいのかわからないもの。ママの育て方が悪かった、甘やかしすぎたからHSCになったという後天性のものでも遺伝でもありません。
したがって、子どもに「なんでこれが嫌なの?」「できないの?」と聞くのは絶対にNG。ただ「この子の個性」と親は認めてあげて、ありのままの子どもを愛してあげるとよいでしょう。必ず家族は子どもの味方になり、どんなことがあっても「家にいれば大丈夫」と安全基地になってあげるのが一番です。
夫婦の話し合いは子どものいないところで落としどころを見つける
HSCにとって、自分の言動や不登校を理由に両親が言い合いするのはとてもつらい状況です。ママとパパにも意見がありますし、ときには言い合いになることもあるでしょう。
例えば、

「男の子なんだから部活は運動部に入らないと!帰宅部は絶対に許されない」

「そう言っても、あの子は身体を動かすのもチームスポーツも好きじゃないんだから」
こうした話し合いは実は大切です。ただし、夫婦で教育方針をそろえるためにも、子どものいないところで落としどころを見つけましょう。
ママがHSCに気づいているのだとしたら、パパにもきちんと説明をして理解を求めます。反対にパパが子どもの気質に思うところがある場合もあるため、夫婦で子どものことをきちんと話し合えると理想的です。
子どもが相談してくるまではじっと待つ
不登校になったら、「ずっと学校に通わないのではないか」「一度許すとずっと不登校のままかも」と不安になります。仕事のあるママは、いつまでも休んでいられないのも事実です。
ただし、子どもが限界を迎えて学校にどうしても通えない場合、無理に登校させるべきではありません。子どもがどう思っているのかを相談してくるまでは、普段と変わらず接するようにしましょう。
ママが「不登校をやめさせないと」と焦ると、その焦りやイライラは子どもに伝わります。HSCは特に考え込みやすいため、むしろ堂々とふるまうとよいでしょう。
小学校に行けなくなっても、家庭での学習で中学校から通った子もいます。また、人間関係をうまく築けなくて公立中学校ではなく私立への進学を決めた家庭もありました。小学校に通うことだけができることでもないため、選択肢をたくさん用意して子どもが気に病まない方法を探っていくとよいでしょう。
こうしたHSCの小学校トラブルは、同じくHSCを持つ先輩ママが情報をたくさん持っています。経験談を聞くだけでも参考になるため、SNSなどで情報交換をしてみるのもおすすめです。
HSCの不登校についてこちらの記事でも詳しくお伝えしています▼
子どもが極度に怖がり…。これはHSC?

HSCの気質上、失敗や危険を考えすぎるあまり極度に怖がりを見せることがあります。当ブログでも子どもの意欲やチャレンジ精神を育む大切さをお伝えしていますが、親としては「いろんなことに怖がらずに挑戦して欲しい」と思いますよね。また、そういう子こそチャレンジ精神のある素晴らしい子どもだと認識しているかもしれません。
ではHSCは怖がりで意欲がなく、その点を直したほうがよいのでしょうか。HSCと怖がりについてここからは解説していきます。
怖がりの子ども、意欲が少ない子ども
HSCは確かに物事に取り組む前に、失敗する可能性や危険を考え込んでしまうために怖がりが出てしまいます。例えば、
- 遊園地のアトラクションはすべて怖がる
- 野外遊びが消極的で外に出たがらない
- 初めて訪れる場所では親のそばから離れない、楽しめない
などはHSCの持つ特徴です。
親としては楽しませるために遊園地に連れてきたのに、身体を動かして欲しいからアクティビティを用意したのに…とがっかりするかもしれませんね。しかし、子どもの定番の楽しみが当てはまらないことだってたくさんありますし、人には個性があって当たり前です。
無理やり子どもに何かをさせると、余計に「ママはわかってくれなかった」と信頼されなくなります。気持ちが安心することがなくなり、不安定になってしまうでしょう。
まずは、「こういう子もいるんだな」とママが理解を示すのが大切です。
子どもの怖がりを克服するには?
とはいえ、子どもの怖がりが極端だと何もできなくなってしまいます。成功体験を積んで子どもに積極的になって欲しいし、そのほうが楽しくなるのに…と歯がゆい思いをしますよね。
HSCが怖がりを克服するには、
- ハードルを思いきり下げて小さな成功体験を積み重ねる
- 無理強いさせず子どもの興味のままにサポートする
- 代わりの物事(スポーツならチームプレイではなく一人でできるものなど)を用意する
- なぜ怖がるのかを調べて考える
などがおすすめです。
一度成功すると「なんだこんなことだったんだ」と子どもが分かってくれることもあります。小さなうちからこうした成功体験を重ねると、大きくなったときに心の支えになってくれることも。決して無理にさせようとせず、子どものペースで物事に取り組む姿を一番の応援者として見守ってあげましょう。
怖がりはメリットになることもある
怖がって新しいことに挑戦しない、思い悩むあまり取り組みが遅いというのは、決してデメリットばかりではありません。むしろ、子どもが自分にはできない、辛いと思っているのに親が無理やりさせることで失敗し、イヤな思い出を作るよりもよっぽど避けた方がよいこともあります。
怖がりは、見方を変えると危険予知がしっかりできているとも言えますよね。また、やらせたいと思っているその経験は、その子にとって本当に必要なのかを大人が一度立ち止まって考えるのも大切です。何よりも子どものことを思っているのなら、子どもの個性や才能を生かせる経験をたくさんさせてあげましょう。
HSCの怖がりはこちらの記事もチェック▼
まとめ
HSP、HSCは生まれ持った気質であり、人よりも繊細で感受性の高い人のことを指します。生活する中で「普通とは違う」部分で悩むことも、社会になじめず歯がゆい思いをすることも多いかもしれません。ですが、現代は以前と比べるとどんな気質の人も自由に個性を発揮しながら生活できる多様性が進んでいます。
我が子はHSCだと気づいたママは、その特徴を正しくしっかり理解しましょう。その上で親は親、子どもは子どもの人生を楽しみ満喫できるのが理想的です。HSCも我が子の個性のひとつ。子どもに合わせた関わりを持ち、大人は子どもの興味や意欲を認めてサポートしてあげましょう。
【参考】
【子育て・育児が辛い!】HSP(繊細さん)の特徴と楽になる考え方 | こそだてまっぷ
HSPの適職65選!HSPの特徴と強みを活かす方法を解説|Like U ~あなたらしさを応援するメディア~【三井住友カード】
















<HSPの特徴である「DOES」>
取り込んだ情報をじっくりと捉える傾向にある。
刺激を受けると神経が高ぶりがち。
共感性が高く気持ちが強く反応しやすい。
五感などの感覚が鋭く、人が気付かない部分に気づきやすい。