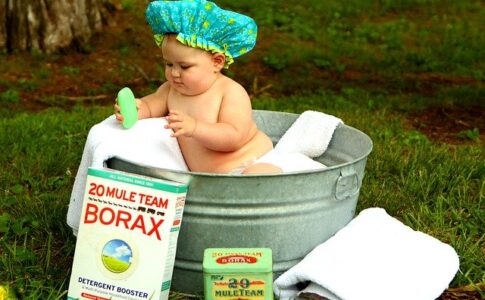べき思考とは、「~~すべき!」という育児中のママが陥りやすい考え方の癖を指します。育児とは一人ひとりが異なる方法でしかできないのに、世間一般からの「育児中ママ」というイメージが固定されているために、ママは「理想のママ像」と「そうはならない現実」の中でストレスを溜めてしまいやすいのです。
べき思考を続けていると、いずれママ自身だけでなく家族もストレスフルな状態になることも。そこで、この記事では「べき思考をやめる方法」を詳しく解説していきます。
- 自分のべき思考が手放せず困っているママ
- どうしても他人に厳しくしてしまうママ
- すべて完璧にこなさないと気が済まないママ
- べき思考とは何か、何が原因でべき思考になるのかを解説
- べき思考の直し方をわかりやすく解説
- べき思考についてママが気を付けたい3つのポイント
「べき思考」に支配されていない?育児中のママに起こりやすいこと

べき思考とは、簡単にいうと「~~すべき」とすぐに考えてしまうことです。べき思考を一切持たない人はいませんが、べき思考に陥りすべての考えがネガティブになってしまうと、ママ自身や子ども、家族や人間関係にも影響が及びます。
まずはべき思考とは何かをチェックしていきましょう。
べき思考とは
べき思考とは、ご紹介の通り「〇〇するべき」「〇〇しないといけない」という思考を指します。その〇〇に当てはまるのは、「性別」「職業」「年齢」「環境」などさまざま。ママ自身も「母親なんだからこうしなくちゃ」「子どもを優先にして当たり前」と自分の考えを強制してしまうことは1度や2度ではないはずです。
なぜべき思考が生まれるのかというと、さまざまな原因があります。よく考えられているのは、幼少期の頃から身についてしまった「認知の歪み」です。
たとえ母親だとしても、正しい服装や趣味、子どもを優先するかどうか、どんな育児をするのかは個人の自由。しかし、幼少期の頃から思い込んでいる「理想の母親像」「世間から求められている母親像」がある人は、実際に自分が母親になるとべき思考に陥り抜け出せなくなるのです。
ママ自身に向かうべき思考
育児中のママはべき思考に陥りがちです。例えば、ママ自身に向かうべき思考を見てみましょう。
- 母親なんだからこれくらい我慢して当たり前
- ママは子どもを優先するべき
- 育児書通りの育児をするべき、育児を学ぶべき
ついこう思ってしまうこともありますが、このべき思考はこだわりが強く、またママ自身に向かうべき思考をすべてこなすのは不可能です。「我慢して当たり前」「ちゃんとできて当たり前」と自分の行動を認めてあげられないと、ママ自身の自己肯定感が下がりストレスも溜まってしまうでしょう。
子どもやパパ、他の人に向かうべき思考
べき思考の厄介な部分は、自分だけでなく他人にも「~~すべき」と思ってしまうことです。
例えば、以下のようなべき思考には注意が必要といえます。
- パパは家事や育児を進んで代わるべき
- 子どもだからこのおもちゃで遊ぶべき
- ママ友に対して「あの人の服装や振る舞いは母親らしくない」
こうしたべき思考は他人に対して厳しく見てしまい、自分の意にそぐわないことにイライラしたり、相手を自分の思い通りにしてしまったりと問題行動が増えてしまいます。自分に置き換えて考えてみるとわかるのですが、「他人が家庭や自分の生活に対して物申してくる」というのはストレスが溜まりますよね。この状況が続くと、対人関係にも影響が及びます。
べき思考をやめる方法

「自分にとってストレスになる」「他人にも厳しく当たってしまう」。こういったべき思考を改善する方法はいくつかあります。
ここからは、べき思考をやめる方法をわかりやすい言葉で解説。ゆっくり自分の中の「問題がある思考の癖」を取っていきましょう。
「これ、べき思考!」と思ったら書き留める
日々の暮らしの中で、べき思考はさまざまなところに現れます。例えば、子どもの寝支度に時間がかかり、いつもよりも寝る時間が遅くなってしまったとき、ママとしては「子どもは早く寝るべき」と焦ってしまいますよね。夕食の準備ができなかった日などは、「子どもには冷凍食品や出来あいのものは食べさせてはならない」と罪悪感でいっぱいになるかもしれません。
ですが、よく考えると「たったその日だけ寝るのが遅くなっただけで、子どもが寝不足に陥るわけでもない」「ママだって夕飯が作れないときは当然ある」と気づけるはず。ここに「べき思考」が隠れているのです。
まずは、このべき思考に自分で気づき、簡単に描き留めましょう。気づいた瞬間にスマホのメモ帳機能を使っても良いですし、1日の終わりに振り返って日記に書き留めても構いません。
1日の終わりにその日の「べき思考」を書き換える
べき思考を書き留めることができたら、次は1日の終わりに振り返ってみましょう。ここで、「今日はべき思考が起こったことはないかな?」と書き出しても大丈夫です。
べき思考を見つけたら、次は書き換えます。
- 子どもは早く眠るべき→別に早く寝なくたって構わない
- 夕飯は手作りするべき→毎日手作りする必要はない
- ママは疲れた、やりたくない、と言ってはならない→ママだって疲れるときがあっても良い
ここで書き換えることで、べき思考がいかに現実的でないかに気付くはずです。書き換えられないべき思考は、生活を営む中で欠かせないものしか残りません。
同じことが起きたら…自分を褒めよう!
この「べき思考に気付く→書き出す→書き換える」を繰り返すと、そのうちにべき思考が生まれる瞬間、さらには自分の中で書き換える瞬間、意識が変わるときがやってきます。例えば「子どもが寝支度に手間取って寝る時間が遅くなってしまった。でも、まあそんな日があってもいいか」と思えるときです。
こうしたべき思考が改善できたときは、自分を褒めてあげましょう。ママの中で直したい思考の癖はこのように取ることができますし、柔軟な考えを持つことで周囲にも優しくなれます。
べき思考をやめるときに気を付けるポイント

べき思考をやめる方法をご紹介しましたが、実は「べき思考に陥っているママほど注意することが多い」のが実情です。なぜなら、思考の癖はなかなかとることができず、自分でも「やめたほうがいいのに」と自己コントロールができずにストレスにつながるからです。
そこで、ここからはべき思考をやめるときに気を付けたいポイントを解説します。
「べき思考」をやめるべき!に注意
べき思考は絶対にやってはならない!と思ったママは、こう考えたのではないでしょうか。
「べき思考をやめるべき」
これだと、さらにママの中の固定概念や強制は続いてしまいます。べき思考はママが「正しい母親でありたい」と頑張った結果であり、これをやめるために「自分はべき思考もやめられないダメな母親だ」と思うと悪循環が続いてしまうのです。
特に真面目なママにこそこうした「べき思考をやめるべき」に陥ってしまうため、まずは日々のストレスを緩和し、気持ちに余裕を作ることから始めましょう。
「べき思考をやめること」を他人にも押し付けない
べき思考をやめると、意外と世の中にはべき思考がたくさんあることに気付けます。例えば、みなさんの親世代では「育児は苦労してこそ」「私も大変だったのだから今のママも大変であるべき」と押し付けてくるかもしれませんね。
ただ、この考えも「排他すべき」ではありません。人の数だけ、さまざまな意見があるのが当然。周囲のべき思考に気づいたとしても、他人にべき思考をやめるよう押し付けるのはおすすめできません。
べき思考をやめられない自分を責めない
べき思考=認知の歪みとは、身に着いた考えの癖を直すことが必要です。無意識のうちに考えてしまう癖を直すのは、たっぷり時間が必要なことを頭に入れておきましょう。
たった今、べき思考をやめられるかというとそうではありません。たまにはべき思考が出てくるかもしれませんし、なかなか簡単には無意識の思考の癖は取れないかもしれません。
けれどもママはそんな自分を責めることなく、寛大な気持ちで向き合ってみると良いでしょう。
まとめ
育児中のママを苦しめる「べき思考」。やめる方法や改善手段はたくさんありますが、まずは「ゆっくりと自分の認知の歪みに気づき、受け入れ、書き換える」のが大切です。
たった今大変な思いをしているママも、本記事を参考に焦らずにゆっくりとべき思考の癖を取っていきましょう。
【参考】
べき思考を手放すには?認知のゆがみを生む原因や具体例、改善方法を紹介 丨コグラボ- Cognitive Behavioral Therapy Lab