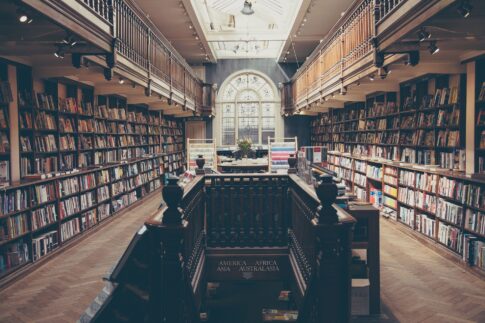ソーシャルスキルトレーニング(SST)という言葉を聞いたことがありますか?このSSTは特に発達に特性のある子にとって効果的といわれています。
病院や療育でも取り入れられているSSTですが、調べてみると有料の教材と無料の教材に分かれていますよね。「無料のものは意味がないのでは?」と不安に思うママもいるかもしれません。
今回はSSTを家庭内で取り入れたいママに向けて、無料の教材って意味があるの?という点を深堀りしてご紹介。子どもとママの心の発達や成長を見守る当サイトの視点で解説します。
ソーシャルスキルトレーニングとは?資格や施設で受けなきゃダメ?

まずはソーシャルスキルトレーニング、SSTとは何かをご紹介します。「なんとなく聞いたことがあるけれど、実態はよくわからない」というママは参考にしてください。
SSTとは
SSTとは、対人関係や社会的な状況に適応するスキルを訓練で身につけるものです。社会人として生きる上で、私たちは必ず家族以外の他者と関わらないと生きていけませんよね。こうした対人関係に対して、立場や状況をきちんと読み取って適切な態度を取りますが、このやり取りは誰しもができるものではありません。
特に発達障がいなど、特性がある子にとっては「他人の気持ち」を理解するのはとても難しいものです。また、自分の気持ちをうまく伝えられなかったり、自分の思い通りにならないときに気持ちの切り替えが難しかったりと、対人関係や状況判断は複雑に自分の気持ちをコントロールしなくてはなりません。
この生きるための力を育む訓練が、SSTです。
SSTを行うには資格や施設が必要?
SSTは特に療育や病院で取り入れられることが多いです。対人関係を築くのが苦手とする子は、こうした専門施設を利用したことがあるかもしれませんね。SSTはこのような施設でも受けられますが、実はSSTを実践するのに特別な資格や状況、決まったテキストなどはありません。とはいえ専門性の高いものはSSTのコースやワークショップ、サロンなどがありますが、必須ではないため家庭に合う方法を選ぶとよいでしょう。
自宅でSSTをする方法とは
特別な資格や環境も必要としないSSTは、ママがやり方を理解して家庭で実践することもできます。ただ、SSTといっても授業や座学ではないため、子どもと目的を持って遊ぶだけでOKです。
さらに日常生活の中でもSSTを意識することはできるため、記事後半の家庭で行うソーシャルトレーニングのコツもあわせて参考にしてみてくださいね。
ソーシャルスキルトレーニングの無料教材、効果はあるの?

SSTを調べてみると、カードやすごろくなどのボードゲームセット、学習プリントやワークシートなど、教材が販売されていますよね。一方で、無料で公開されている教材もあります。
この無料教材は何となく「タダだから信用できるのかな?」と不安になるかもしれません。そこで、教材は無料と有料どちらがよいのかを今一度考えてみましょう。
子どもに合う教材ならOK
まず、教材は必ずしも有料のものが信用できるかというとそうではありません。また、有料でも意味がないというわけではなく、大切なのは子どもに合うかどうかだからです。
SST向けの教材とは、ネットを調べるだけでも多数見つかります。療育や病院で取り入れられるものも、数多くの種類が用意されていることでしょう。
教材が多数あるのは、子どもにとって合う教材は細かく異なるからです。教材の理解がしやすく、楽しめるものであれば有料か無料かは関係なく使うとよいでしょう。
遊び方にも工夫を
遊び方や教材の進め方は、その橋座の指定通りでなくても構いません。例えばカードゲームで勝ち負けがある場合、勝負が苦手な子にとっては取り組みにくいものになってしまいます。
SSTの目的は教材やゲームによって、日常生活の中で必須のやり取りや語彙力、表現力やコミュニケーション能力を育むことです。その目的が達成されることこそ大切なので、勝負をなくしたり「パスをしてもいい」とルールを決めたり、負けても泣かない、周りに「早くして」と言ったりバカにするようなことを言わないなど、独自の基準を設けても構いません。
有料教材と無料教材の違いとは?
では、有料教材と無料教材の違いはどんな点があるのでしょうか。教材の種類にもよりますが、有料のものは種類が豊富だったりすでにカードの形式になっていたりするため、SSTをする際に使いやすいというメリットがあります。
無料でダウンロードできる教材だと、どうしてもコピーをして組み立て、手作りでワークシートやカードなどを作らないといけません。また、無料のものはどうしても種類が限られてしまうため、子どものSSTとしての遊びの幅が制限されてしまうというのもネックとなるポイントです。
とはいえ、無料のものでも長く使える優秀な素材は多数見つかります。まずは無料の教材で試してみて、子どもに合うと思ったら買い足してみるとよいかもしれません。療育や病院で受けるSSTの様子もよく観察して、子どもが興味を持つものをチェックすると日々の生活に役立ちます。
家庭で行うソーシャルスキルトレーニングのコツ

無料の教材でも十分役に立つとわかったら、早速家庭で取り入れてみたいですよね。家庭でのSSTは難しいことを考える必要はありませんが、コツを掴むとより効果が期待できます。
家庭で行うSSTのコツをチェックしてみましょう。
SSTは「遊び」を交えて
SSTは学習というイメージを持つママも多いのですが、あまり堅苦しいものではなく子どもに合わせて柔軟にルール変更ができる「遊び」です。SSTをきちんとしないと!と決めてかかってしまうと、子どもは意欲をなくして楽しみがなくなってしまいます。
遊び感覚で楽しめるとより続けやすくもなるため、ゲームをするように親子で取り組めるとよいですね。
コミュニケーションを取りながら
例えばSSTでカードゲームなどをする場合、ただルールにだけ則って淡々と進めるのではなく、
- 「こういうときどう思った?」
- 「ママはこう思った」
など会話をたくさんかわしながら進めるとベストです。
SSTの最終目的とは、この記事冒頭でもお伝えしたように「社会的なやり取りを円滑にするためのトレーニング」です。SSTの間にも楽しみながら親子のコミュニケーションをとることで、効果がより実感できるようになります。
「できた」「わかった」という体験を大切に
できた、わかったという感覚は、大切な成功体験です。「できて当たり前」ではなく、子どもが意見を言えるようになったら、ゲームを正しく理解できるようになったらきちんと認めてできるようになったことを喜びましょう。
ママが笑顔でいると、子どもはより嬉しくなります。SSTといっても親子間のコミュニケーションに他ならないため、難しく考えすぎずに「遊びの一種」と捉えて楽しめると理想的です。
まとめ
ソーシャルスキルトレーニングの教材。今ではインターネット上だけでなく、インスタグラムなどのSNSでも配布しているものをよく見かけます。無料だからこそ信用性が気になることもありますが、無料と有料はさほど大きく影響せず何より子どもに合うものを選ぶのが大切です。家庭でもSSTは実践できるため、ぜひ親子に合う方法を見つけてみましょう。
【参考】
こんな時どうする? | 専門家が作る子ども向け無料プリント『やんちゃワーク』
ソーシャルスキルトレーニングができるお家プリントワーク無料配布中!低学年の子が学校生活を楽しむソーシャルスキルを育てよう【教材付】 | パステル総研
発達障がいの子どもが遊びの中で訓練できるソーシャルスキルトレーニング | 放課後等デイサービス みらいジュニア- weblio英会話